2022年10月6日(木曜日)より放送をスタートし、
ギャラクシー賞の2022年12月度月間賞を受賞するなど、
そこで、この記事では、ドラマ「silent(サイレント)」
その前に、まずは、ざっくりとドラマ「silent(サイレント)」
すでにストーリーやキャスト陣を把握しており、
目次
ドラマ「silent」の登場人物
青羽紬(あおば つむぎ)
演:川口春奈
…本作の主人公で、中途失聴に悩まされる同級生・
佐倉想(さくら そう)
演:SnowMan・目黒蓮
…高校卒業後に若年発症型両側性感音難聴を患い、
井草華(いぐさ はな)
演:石川恋
…旧姓は佐倉で、想の姉。弟の病が遺伝することを心配し、
佐倉想の甥「優生」の名前が炎上した理由
後天的に難聴を患い、後に完全に聴覚を失った想ですが、その姉・
これは、“障害者差別“とも非難され、
炎上理由①:「優生保護法」との関連
この「優生保護法」とは、
もちろん、表向きの施行理由は「母体保護」ですが、
障害を持つ人に強制的に中絶や不妊手術をさせる条文も備えている
つまり、劇中で難聴の遺伝リスクがあった華の新生児は、
結果的に遺伝はなく、元気に産まれてきたわけですが、
「単なる偶然ではないか?」とする声もありますが、
炎上理由②:助産師だった「silent」脚本家・生方美久

2023年2月28日に配信されたライフスタイルメディア「
生方氏について、
「もともとは助産師として働いていたものの、『
との説明があります。
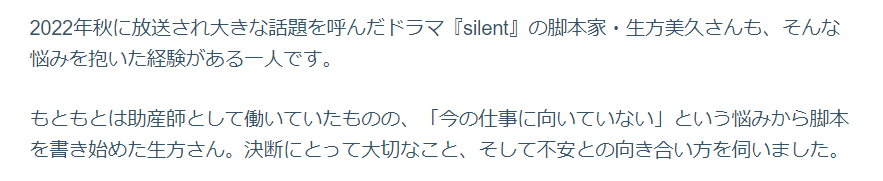
また、これまでにも、
炎上理由③:字幕で初めて判明した「優生」の漢字表記
劇中で、華は「優しく生きてほしい」との願いを込めて、「優生」
しかし、当然ながら、ドラマ本編の中では「ゆうき」の漢字が「
そうした点もまた、“何らかのメッセージ性を感じる“
名前を「優生」としたことについての意図は、最後までドラマ側、
しまいには、「特定非営利活動法人」が「silent」
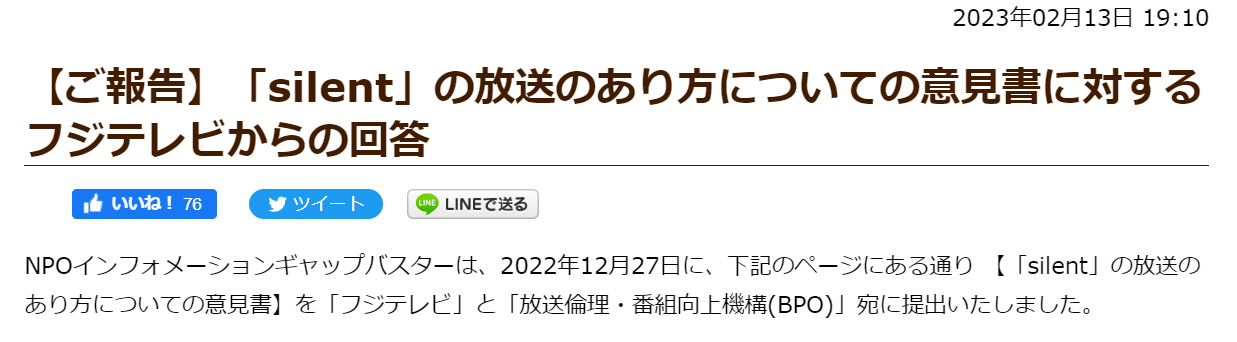
もちろん、
「silent(サイレント)」